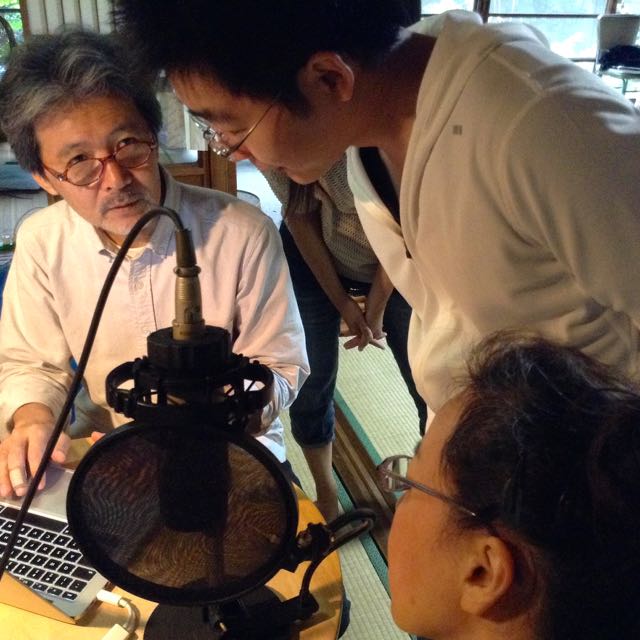アルチュール
(C)2018 by MIZUKI Yuu All rights reserved
Authorized by the author
アルチュール
水城ゆう
もたもたとお茶をいれるその手際のわるさに、私はいつものようにいらだってしまう。二a型の学習アルゴリズムに問題があることは承知の上で彼を購入したのだが、茶を所望したときはそれを後悔する。
「いったでしょう、アルチュール。茶葉は倍以上使って濃くしないと飲めたものじゃないって。そんなふうにとろとろいれない! 冷やすときは一気に氷に注ぐのよ」
私のとげのある口調に彼はびくっとなり、さらに動作が鈍くなる。その感情反射アルゴリズムは頭の悪いパブロフの犬のようだ。
いつまでもそんな風だと廃棄だからね。いつも思うこれは口に出さない。そのかわり彼に注文を出す。
「なにか詠んでちょうだい、アルチュール。なんでもいいけど……そうね、テーマは紅茶で」
彼は一瞬かんがえ、すぐに口を開いた。
そんなときはよどみない。しかも私のためにアイスティーを運んでくる動作もまったくとどこおりなく。
おれの魂は琥珀の酒
ただれた溶岩を伝って
冷たい世界の化石となる
未来永劫ここから見張れ
淫らな女どもを
聴きながら私はいつわりの優越感にひたる。二a型のアンドロイドを所有する身分。とはいえその私も三d型という、いまや骨董品にちかい型式の人工知能搭載ヒューマノイドではあるのだが。