ゼミ通信:自主ゼミレポート
〜Facebookで野々宮卯妙が書いた自主ゼ […]

自分に嘘をつかない

基本は共感とマインドフルネス
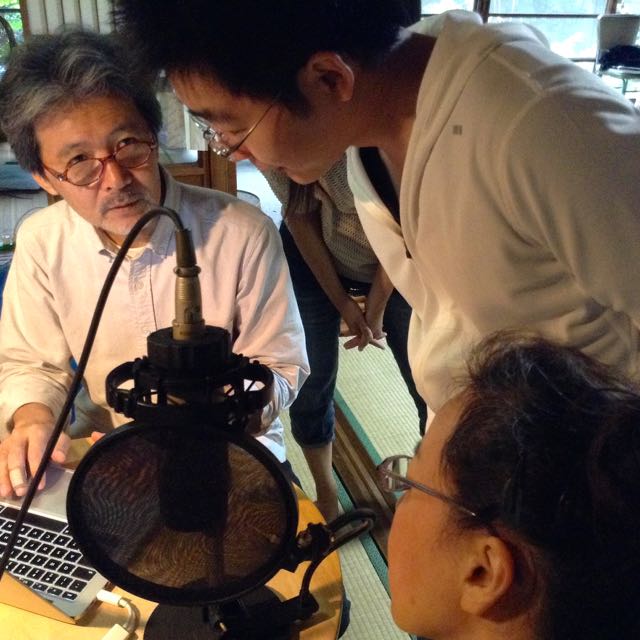
音声・文章コンテンツの自作・発表をサポート
〜Facebookで野々宮卯妙が書いた自主ゼ […]
現代朗読ゼミ、すべてオンラインに移行して1ヶ […]
現代朗読ゼミ生が個人レッスンを受けるタイミン […]
(C)2019 by MIZUKI Yuu All rights reserved
Authorized by the author
事象の地平線――イベントホライズン
あの丘を越えれば
無限の波と雲が迎えてくれるとわかっているのに
おまえは死の影におびえながら歩《ほ》をためらっている
なにをしようにも
なにをいおうにも
なにかを思い出し
思考と観念の痛みが
ただ積み重なり
がんじがらめになる日々に
おおわれたのはいつからなのか
おまえはもう思い出すことができない
ほら
もうそこに見えている
丘を越えよ
一歩踏みだせ
すべてを呑みこみ
すべてを断《た》ち切る
降着《こうちゃく》円盤《えんばん》が
まばゆく輝いている
そこは時と光が引きのばされ
あらゆる事象が人知《じんち》を超える
イベントホライズン
闇の此岸《しがん》に
我らの地がある
*
いただき物の菓子箱を包んでいた包み紙の皺《しわ》を、きみは丁寧《ていねい》にのばしている。テーブルの上に紙をひろげ、隅々《すみずみ》まで手のひらと指の腹を使って、皺をまっすぐにしている。皺がのび、紙がまっすぐになると、きみはそれを半分に折る。端《はし》と端を合わせて、まずは長いほうからふたつに折る。角《かど》が正確に合っているのを確かめ、真ん中に折り目をつける。
包み紙が半分になったら、さらにもう半分に折る。今度も角が合っているのを慎重に確かめ、きっちりと折り目をつける。さらにもう半分。四つ折の新聞紙ほどの大きさになると、きみは立ちあがり、物入《ものい》れの引き戸をあける。
物入れには整理棚があって、段のひとつにきれいに折りたたんだ包み紙が何十枚も重なっておさめられている。いまたたんだばかりの包み紙をきみはその上に乗せ、そっと手のひらで押さえて厚みの感触をたしかめる。
*
おまえはまたうっかり、いつものようにろくに噛まずに肉の塊を飲みこもうとして、胸を押さえる。狭くなり、食べ物を胃へと送りこもうとする蠕動《ぜんどう》運動が鈍《にぶ》っている食堂に、とんかつのひと切れが引っかかって止まる。
痛みと息苦しさで、おまえは涙目《なみだめ》になりながら、テーブルの上の水のコップに手を伸ばす。水を飲む前に、なかば無意識にこぶしを作った手で胸をとんとんと叩く。そんなことをしてもなんの効果もない。
水をひと口ふくみ、飲みこむ。水は食道をふさいでいるトンカツのところで止まり、冷たくたまる。痛みをこらえ、待つ。水はやがて、肉塊《にくかい》のすきまをとおり、食道を通りぬけていく。それにつれて、引っかかっていた肉塊もするりと動きはじめ、ゆっくりと胃へと降りていく。
痛みが引いていく。おまえはほっと息をつき、胸をさする。その奥にあるイベントホライズンを思いながら。
*
きみは大根を切ろうとしている。これから味噌汁を作ろうというのだ。葉の根元が残っている首のところをザクリと切り落とす。落とした首は捨てないでまな板の横に取っておく。つづいて五センチくらいのところで横に切る。円筒形ができる。包丁を皮にそってあて、大根の皮を薄くそぐように切りはいでいく。皮をはいだ大根は縦に切れ目をいれて、太いマッチの軸のような形にすると、水を張った小鍋にまとめて入れる。皮も捨てずに取っておく。
つづいて人参《にんじん》を切る。葉がついたままだ。おなじように根元《ねもと》を切り落とす。皮はむかずに、大根のように、しかしもっと細い軸になるように、刻んでから小鍋《こなべ》に入れる。首についている葉は外側のものを何本か指でちぎってきれいなものだけ残すと、そのまま水を張った小皿に乗せる。大根の首も別の小皿に乗せる。
それらを窓際《まどぎわ》に並べる。こうやっておくと、大根からも人参からもあたらしい芽が出て、あたらしい葉が伸びて彼の目を楽しませてくれるだろうと、きみは思っている。
*
おまえは浜辺でそれを見つけたのだ。波はちいさく、サーフィンの合間に波打《なみう》ち際《ぎわ》で休んでいた。手をうしろに突き、両脚を投げ出して波に洗われままにしていた。指先になにかが触れて、おまえはそれをつまみあげた。貝の死骸か小石だろうと思った。
目の前にかざしてみると、それは自然のものではなく、あきらかに小さくて丸い人工物だった。ビーズ玉というにはすこし大きい、ペンダントというには小さい、大きめのイヤリングか丸いボタン、とんぼ玉のような、材質は木ではなくおそらく石または金属、表面にはこまかな彫《ほ》り物がしてあり、古代文字のような模様が浮かびあがっている。梵字《ぼんじ》のようにも見えるが、梵字ではなく、おまえが見たこともない文字だった。
文様は浮き彫りなっているようだが、よく見ると透《す》かし文字で、掘りあげられた文字の奥にさらになにか透けて見えていた。
かすかに光っている。しかもその光がちらちらとまたたいている。光源そのものが動いているようにも見えた。
なぜかわからないが、おまえはそれを口にいれてみたい衝動にかられた。なめてみたくなったのだ。
おまえはそれを口にいれた。舌の上にころがしてみると、思いがけず焼けるような熱を感じた。吐きだそうとするおまえの意志に反して、それは舌の上をころがり、喉の奥へ向かった。焼けるような熱さと痛みに、おまえは思わずそれを飲みこんだ。
*
きみはくねくねと扱いにくい細長いホースの先端を苦労してバスタブにいれる。バスタブには昨夜の残り湯がある。風呂蓋もホースも取りまわすたびに水滴が飛び散って、せっかく拭《ふ》きあげた風呂の床を濡らしてしまう。スリッパを脱げばいいけれど、靴下もいっしょに脱ぐ必要がある。
ホースの先端には丸いプラスチックの口がついていて、そこから残り湯を吸いあげるようになっている。ドラム式の洗濯機で残り湯が使えるようにするのに、きみはとても苦労した。いろいろ調べて金具を取りよせたりして、やっと使えるようになった。たとえ残り湯といえども、そのまま下水に流してしまうにはしのびない。洗濯に使う分にはまったく支障はない。残り湯を最後まで使いきることが、きみには重要なことなのだ。
*
マイクロブラックホールは、そのシュヴァルツシルト半径が量子サイズのブラックホールである。ミニブラックホールとも呼ばれる。ブラックホールの質量はシュヴァルツシルト半径に比例するため、質量もそれに応じ小さいが、量子サイズであることを考慮すればきわめて大きい。
ブラックホールを記述する一般相対性理論のシュヴァルツシルト解《かい》は、任意の質量のブラックホールを許容するが、当初はこのような極微《きょくび》のブラックホールを生成する現象は知られておらず、存在しえないと考えられていた。しかし、ビッグバン直後の高エネルギー状態の中で発生した可能性がある。
*
目覚めたとき、たしかにおまえは彼女の気配《けはい》を感じる。彼女の気配を感じている自分を感じる。おれはまだ生きている、と思う。それから「まだ」というのはおかしいなと思う。「まだ」でもなく、「さらに」でもなく、「もう」でもない。「いま」だ。目を閉じたままかんがえをリセットする。おれはいま生きている。
息をしている自分に気づく。生きている自分。息を吸い、吐いている自分。胸郭《きょうかく》の内積《ないせき》が増加すると、ふくらんだ肺に臓器が圧迫される。食道が押され、脊椎《せきつい》とのあいだにある組織から痛みが生まれる。
組織はあの物体を包みこんで肥大化している。歴史が生まれるはるか以前の古代人が、すでにうしなわれた技《わざ》を使ってあれを作った。原初宇宙の黒い力を閉じこめる技。
黒い力は時間と空間を支配する。おまえも時間と空間に支配されている。すべての人間、生き物、存在が、宇宙の時間と空間に支配されている。黒い力はおまえの時間と空間をひずませている。
あれを取りこんだおまえの身体《からだ》の細胞は異常な増殖をはじめている。増殖細胞は全身に転移し、おまえの時間をひずませていく。しかしそれは自然なことなのだ。宇宙の法則の一部なのだ。人がそれにあらがうことはできないのだ。
おまえは横たわったまま目をあけ、彼女の気配を感じている自分のひずんだ身体を観察している。彼女はまだ眠っている。規則正しい寝息が聞こえている。それを邪魔しないようにおまえはそっと身体を起こす。
*
彼がきみに気づかれないようにそっと身を起こし、水を飲みに行くのを、きみは目を閉じたまま感じている。
キッチンの流しには昨日の食器の洗い残しがあって、彼はそれを洗おうとしている。湯沸かし器のスイッチを入れる音がする。いくつかの食器を洗うためだけに盛大《せいだい》に、たっぷりとお湯を使うのを、きみはもったいないと思う。しかし、そのことをいうのはもうやめた。いまの彼は冷たい水を使うことがつらいらしい。彼の身体は感覚が鋭敏になったり鈍感になったりしていて、想像がつかないような変化が起きている。
きみにはそれを止めることはできない。彼にもそれを止めることはできない。だれにもどうすることもできないことがある。
*
ふたりがかりで寝台に寝かされ、身体《からだ》の位置を神経質に調節される。胸に直接医療用マーカーで描《えが》かれた青黒い皮膚マークを目印に、照射される光で位置合わせをするらしい。ひとりが両脚を抱えて腰の位置を左にずらす。もうひとりはバンザイの格好にあげた両腕の位置を調整する。一ミリ単位の微妙な調整を繰り返し、やがてオーケーが出る。
動かないでくださいねといい残し、ふたりの放射線技師は部屋を出ていく。巨大な円盤のような照射機がおまえの上におおいかぶさっている。
やがて遠くからブザーの音が聞こえ、放射線の照射がスタートする。なんの感覚もない。実際にはレントゲン撮影の百倍以上の線量のX線が、腫瘍に向けて照射されている。
感覚はないが、腫瘍の奥にある古代の玉が反応しているようだ。目を閉じると作りだされたイメージなのか、それとも実際のビジョンなのか、脳裏にそのようすがまざまざと浮かんでくる。
透《す》かし彫りの古代文字のような文様《もんよう》の奥には、ちらちらと光が動いている。それが照射されるX線に反応するのか、ときにまばゆい閃光を上下に放つ。上下の放射光は、中心部に平たく広がった円盤のような光をつらぬいている。円盤は目まぐるしく回転し、体組織を引きよせ、吸着しているように見える。
降着円盤。そこでは光ですら脱出できない重力の穴にむかって引きよせられた物質が、事象の地平線――イベントホライズンにそって回転している。限りなく光の速度にひとしい高速で回転する円盤上では、時空は無限に引きのばされている。ここでは一瞬が永遠にひとしく、点が無限の空間にひとしい。また時間と空間は重なりあいつつ並行して存在している。
おまえの肉体はそれに向かって収束していく。時間という概念を創り出したヒトの脳世界では、それを死と呼ぶ。
人知を超えた潮汐力《ちょうせきりょく》にとらえられ、おまえは巨大な渦に巻きこまれていく。いったん渦に巻かれればだれもそこから逃《のが》れることはできない。たとえそれがマイクロブラックホールであったとしても、ブラックホールに向かう流れは不可逆なものであり、元にもどすことはできない。しかし、その先にあるものは終焉《しゅうえん》ではない。ゴールではない。死という概念でもない。その先にあるものは認知が不可能な事象の地平線であり、すべてがあると同時にない場所でもある。
やがてまばゆい光のなかでおまえは自分の姿を見る。いま、この瞬間、降着円盤のなかで行く手を凝視しているおまえ自身の姿を、周回軌道をぐるりと追いついてうしろから見る。おまえがいま見ているのは、前を見ているおまえ自身のうしろ姿だ。
おまえはおまえ自身のうしろ姿に近づき、やがて追いこしていく。追いこしたかと思えば、また目の前におまえの後ろ姿がある。それはいまのおまえの後ろ姿ではない。おまえはウェットスーツを着てサーフボードを小脇《こわき》に抱《かか》えている。浜辺を波打ち際に向かっているおまえの姿はいつのものなのか。過去の自分の存在が降着円盤のなかでめぐり、それに追いついたいまのおまえが見ている。
気がつくとおまえの姿が無数に見える。前にも後ろにも、横にも。上にも下にも。まるで巨大なマトリクスのように、あるいは全周囲の合わせ鏡のように、自分のさまざまな姿がめぐっている。はるか上には子どものころの自分の姿も見える。父親に手をひかれ、河原の堤防に植えられた桜の満開のトンネルの下を、生まれたばかりの妹に会いに病院に向かっている三歳のおまえの姿。期待と好奇心に満ちた、同時に不安がよぎる感情の記憶も、物質化してそこにあるがごとく感じることができる。
きみはいただき物の菓子箱を包んでいた包み紙の皺を丁寧に、楽しげにのばしている。そうか、楽しんでいたのか、きみは、とおまえは気づく。切りおとした大根の首を小皿に置いているきみも、それを楽しんでいる。おまえが喜んでくれるかもしれないと想像して楽しくなっている。小皿を窓際に置いて、外からの光で若い葉が緑に透けているのを、微笑みながら見ているきみがいる。風呂の残り湯を無駄なく使うことに創意工夫の喜びを感じながらきびきびと選択しているきみの姿もある。
そうか、ここにいたのか。みんな、ここに、すべてが無限の時間のなかにあるのか、とおまえは気づく。ここにすべてがある。
私の肉体と魂が消失すると同時に、すべてが存在するイベントホライズン。私のなかにあり、また私自身をも含んでいる。
全的理解がここにある。
私はいま、ピアノを弾いていて、ここにいると思っているけれど、本当は宇宙のどこか、イベントホライズンの無限に引きのばされた時間と空間のなかにいるのかもしれない。
私は――あなたは――おまえは――きみはここにいると同時に、ここにいないのかもしれない。
(おわり)
現代朗読ゼミ生が個人レッスンを受けるタイミン […]
現代朗読の映画を作っています。 連続ワークシ […]
※会場が変わりました。ご注意ください。 名古 […]